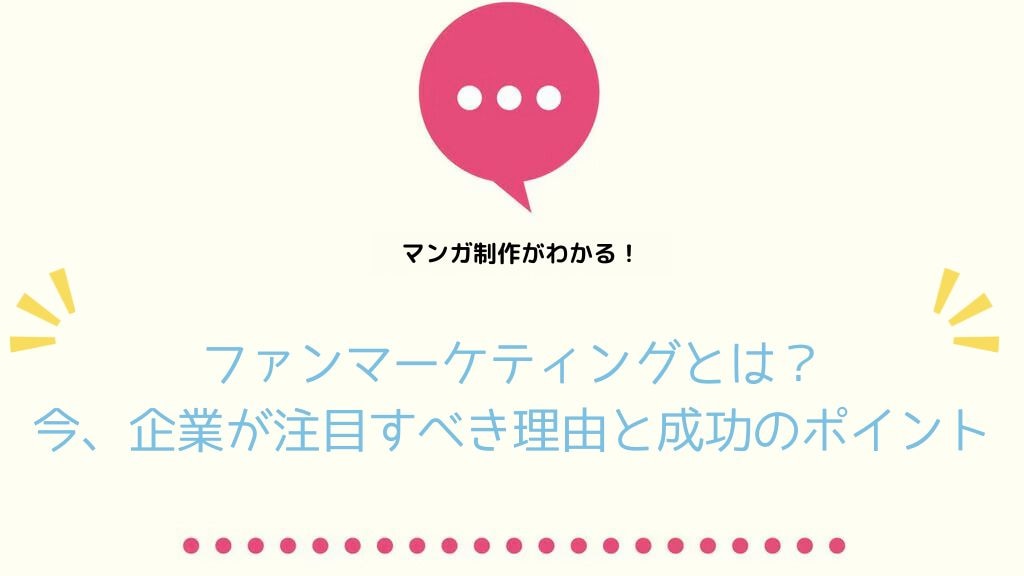
ファンマーケティングとは?今、企業が注目すべき理由と成功のポイント
なぜ今「ファンマーケティング」が注目されているのか
近年のマーケティングやPRの世界を一言で表すと「広告を見ない時代」といえるでしょう。SNSや動画配信サービスの普及により、消費者は従来型の広告をスキップし、自分が信頼できる情報源から商品やサービスを選ぶ傾向が年々強まっています。
また、ここ数年の統計やアンケートで「広告よりSNSの発信やインフルエンサーの発言を信頼する」という傾向も強くなっています。特に、いわゆるZ世代と呼ばれる若い世代にこの傾向が顕著です。実際、ある企業が2025年に実施した大学生対象の調査では、42%がマスメディアよりSNSを信用すると回答しています。
このような状況下で強い影響力を持つのが「ファン」の存在です。
企業がどれほど魅力的なメッセージを発信しても、消費者は企業自身の発信よりも第三者のリアルな声を信じます。SNS上の口コミやレビュー、ユーザー投稿による拡散は、広告費をかけずとも信頼と共感を生み出す強力な推進力です。
こうした背景のもとで注目されているのが「ファンマーケティング」です。これは、単なるプロモーション戦略ではなく、「ファンを中心に据えた経営・ブランドづくり」への転換が、いま企業成長の鍵を握っています。
ファンマーケティングとは
ファンマーケティングとは、自社の商品やブランドを愛してくれるファンを起点に、共感やロイヤルティ(忠誠心)を育て、長期的なビジネス成長につなげるマーケティング手法です。
従来の広告キャンペーンのように一過性の売上を狙うのではなく、関係性の継続を重視するのが特徴です。ファンとの接点を積み重ね、熱量の高いコミュニティを形成することで、ブランド価値の持続的な向上を目指します。
ファンマーケティングの具体的な取り組みには、次のようなものがあります。
- ファンが交流できるオンライン・オフラインのコミュニティ運営
- 限定イベントやファン感謝祭などの特別体験の提供
- ユーザーが参加可能な商品開発や企画投稿(例:ネーミング募集やレビュー共有)
こうした活動を通じて、ファンが自然にブランドの「共感発信者」となり、新たな顧客層への信頼の波及を生み出していきます。つまり、ファンマーケティングとは、顧客を発信者に変えるという発想でもあるのです。
ファンマーケティングと「ファンベース」の違い
ファンマーケティングと並んで語られる概念に、「ファンベース」があります。この2つの概念は一見似通っていますが、その立ち位置には明確な違いがあります。
ファンマーケティングは、ファンを「マーケティング施策」に活かす戦略であることに対して、ファンベースはファンを「経営の基盤」とする思想です。この点が大きな違いといえます。
言い換えれば、ファンマーケティングはファンベースを実践に落とし込むアプローチです。企業のマーケティング担当者にとっては、まず「施策としてファンをどう活かすか」から始めるのが現実的なステップと考えられます。
そして、その取り組みを継続的に磨くことで、最終的には“ファンを軸とした経営”=ファンベースへと進化していくことが理想です。
ファンマーケティング導入企業に見る成功の共通点
ファンマーケティングに成功している企業には、いくつかの共通点があります。単に施策を導入するだけではなく、一貫したファン視点で取り組んでいる点が特徴です。
共通点1:ファンをデータではなく、「人」として理解している
ファンマーケティングに成功している企業は、顧客を単なる数値指標で捉えることはしません。顧客満足度やNPSといった定量データだけでなく、ファンインタビューやコミュニティ内の会話など、定性的なインサイトを重視します。
「なぜこのブランドを好きでいてくれるのか」「どんな体験に価値を感じているのか」これらの感情の背景を理解する姿勢こそが、真のファン理解につながります。
共通点2:ファンとの接点を「施策単位」で終わらせない
例えば、イベントを開催してもその後に経験を活かせず、顧客との関係が途絶えてしまう——これでは意味がありません。
ファンマーケティングに成功している企業は、ファンとの接点を「始まり」と捉え、購入後や参加後も関係を育て続けます。
定期的なメール発信や限定コンテンツの提供、コミュニティでの継続交流などを通じて、共感の輪を絶やさない仕組みを持っています。
共通点3:社内に「ファン視点」を共有している
ファンマーケティングは、マーケティング部門だけの取り組みでは成功しません。商品開発・営業・カスタマーサポートなど、全社員が「ファン思考」で行動できる組織こそが、ファンを惹きつけるブランドを生み出します。
社内でファンの声を共有し、価値観を一致させることで、顧客体験(CX)に一貫性が生まれるのです。
ファンマーケティング成功企業の事例
1.カルビー株式会社

カルビーは、2025年4月にファンと従業員の合計1000人が参加するファンミーティング「Fan With! Project」を開催しました。その後、ファンの中から選ばれた11名は運営企画メンバーとして参加しており、イベントだけで終わらせない取り組みを行っています。
このファンミーティング開催後、参加後の商品購入金額は約1.6倍に増加したと発表されています。
2.ワークマン
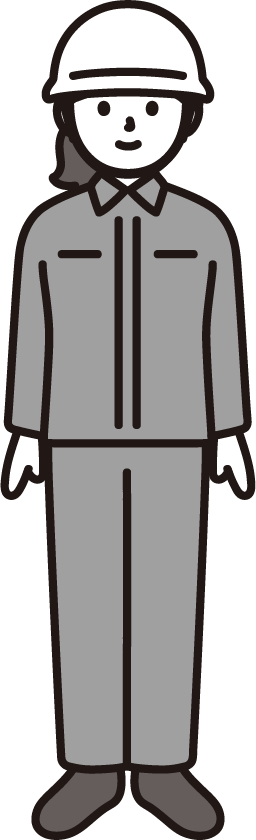
ワークマンは2019年頃から商品の熱烈なファンを「アンバサダー」として起用し、アンバサダーマーケティングを本格的に実施しています。アンバサダーはイベントへの出演、製品開発会議への出席などを担い、同社はアンバサダーを対象とした新商品発表会を開催しているほどです。
実際、アンバサダーを起用することで売り上げが1.4倍に増加したり、アンバサダーの声から生まれた商品が発売されたりと、よい効果をもたらしています。
3.フェリシモ
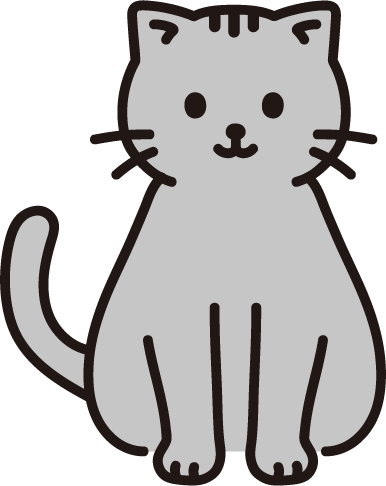
雑貨・アパレルなどの通販事業会社フェリシモには、自社のコミュニティ「猫部」参加者が主催するファンミーティングがあります。このミーティングでファン同士が交流を深め、ロイヤルティの醸成に一役買っています。また、同社はファンの「こんな商品を作ってほしい」「この商品を復刻してほしい」の声を元に商品を生み出す取り組みを行っています。
ファンを「資産」とする発想が、これからの企業成長を左右する
ファンマーケティングは一時的なブームではありません。「広告の到達率が下がる時代」において、信頼されるブランドを築くための必然的な進化です。
熱量を持ったファンは、企業にとって「再現性のある資産」です。新商品の発売初期の購買を支え、SNSで自然発信し、他者の購買行動に影響を与える。こうした好循環が生まれることで、マーケティングコストを抑えながらブランド力を高めることができます。
まずは、すでに自社を支持してくれている“熱量の高いファン”に目を向けることから始めましょう。
彼らと真摯に向き合い、関係を深める。その積み重ねこそが、これからの時代の競争優位を生む原動力になります。

ファンマーケティングとは、企業が顧客を“取引相手”ではなく“仲間”として捉えることから始まります。
ファンの共感がブランドを育て、ブランドの姿勢がさらにファンを生む——この循環を生み出せる企業こそが、これからの時代に選ばれ続けるのです。
トレンド・プロでは、マンガを起点として企業のファンマーケティングをご支援しています。マンガのようなビジュアルコンテンツを活用することで、ユニークなコンテンツになることはもちろんのこと、より感情に訴える形で伝えることができるようになり、顧客のファン化が期待できます。
もしご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
★資料ダウンロードはこちら:https://ad-manga.com/download_form
★お問い合わせはこちら:https://ad-manga.com/contact


