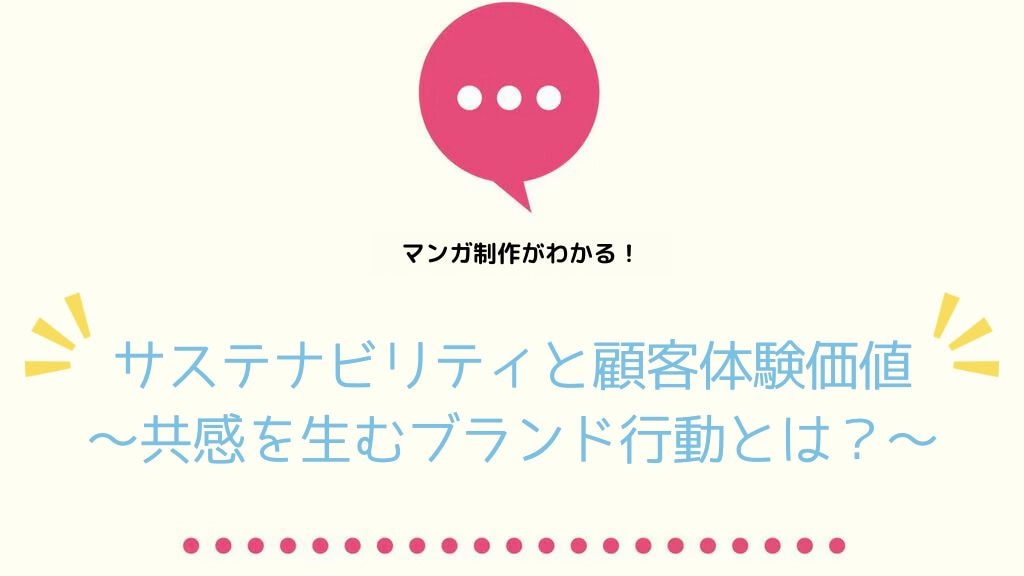
サステナビリティと顧客体験価値:共感を生むブランド行動とは?
かつて、消費者が商品やサービスを選ぶ基準は「価格」や「機能」などが主なものでした。しかし、今は違います。同じような品質や価格帯の商品があふれている中で、人々は「この企業を選ぶ意味」を求めています。そして、その背景にあるのが「共感」です。
なかでもサステナビリティ(持続可能性)への取り組みは、単なる社会貢献にとどまらず、ブランドへの信頼やロイヤルティ、ひいては顧客体験価値(CX)そのものに大きな影響を与えるようになっています。
特に20〜40代のビジネスパーソンの多くは、環境や社会課題に敏感なミレニアル世代・Z世代と接点を持つ機会が増えています。顧客としてだけでなく、社員やパートナーとしても、企業の「姿勢」を見極めようとする目はますます厳しくなっているのです。
今回は、サステナビリティと顧客体験価値の関係に注目し、共感を生むブランド行動のヒントを探っていきます。
サステナビリティとCXの関係とは
まずは、サステナビリティの意味やCXとの関係性を整理しておきましょう。
1.サステナビリティの定義と企業の社会的責任
サステナビリティとは、現在の価値を損なうことなく、環境・社会・経済を未来に持続させていくことを考え、次世代に責任を果たす取り組みのことを指します。例えば脱炭素経営・リサイクル素材の活用・地域社会への貢献など、その形は多岐にわたります。
この考えを背景として、現代の企業に求められるのは、「利益を出すだけの存在」から「社会にポジティブなインパクトを与える存在」へと進化することです。
2.顧客体験価値(CX)の定義と感情的価値の重要性
顧客体験価値とは、顧客が商品・サービスを利用する一連の体験から得る「総合的な価値」を指します。利便性や品質といった機能的価値や価格などに加え、「このブランドを選んで良かった」と思える「感情的価値」が、顧客の心を動かす要素です。
サステナビリティへの真摯な取り組みは、まさにこの感情的価値に直結します。企業の信念や社会への態度は、商品そのものに「意味」を与え、CXの奥行きを深めるのです。
3.「何を売るか」ではなく「どうあるか」
現代の顧客は、商品そのものだけでなく、その背景にある「企業のあり方」を重視するようになっています。例えば、同じ価格のコーヒーが2種類あった場合、自然を破壊し原料を育て、従業員が過酷な環境で働くことによって作られたものと、環境を保護しながら原料を育て、人権や労働環境に配慮しながら作られたものとでは、後者に共感し、選び続ける消費者は少なくありません。
実際、そのことを示すデータはあります。例えば、電通が2022年に実施した調査※によると、調査対象となった日本人消費者の中で、食品・日用品・家電などの消費財を中心にエシカル(≒サステナブル)商品を選択する意向・購入経験が増えていることが示されています。
※ 「エシカル消費 意識調査2022」電通 2022 https://www.dentsu.co.jp/news/release/2022/0620-010527.html
4.一貫性のあるブランドメッセージが信頼を高める
企業のサステナビリティに対する取り組みに求められるのは、「一貫性」です。広告で環境への配慮を謳っていても、実態が伴わなければ顧客は敏感に見抜きます。逆に、言葉と行動が一致しているブランドは、CXにおける信頼性を強化し、長期的な関係構築につながります。
実際、2025年に起こったマクドナルドのポケモンカード問題は、その教訓を浮き彫りにしました。マクドナルドは人気メニュー「ハッピーセット」を購入すると限定のポケモンカードがもらえるというキャンペーンを実施。しかし、ポケモンカードのあまりの人気ぶりから、カードのみを入手して食事を捨てるフードロス問題が多発し、最終的に消費者庁から改善要望を受けるまでに発展しました。
同社はかねてよりフードロス削減を掲げていたものの、この施策では利益追求に傾きすぎ、ブランドメッセージとの矛盾が露呈しました。この一件は、サステナビリティを「掲げるだけでなく貫くこと」の重要性を示しています。
サステナビリティがCX向上につながった企業事例
実際に、企業のサステナビリティへの取り組みがCX向上に寄与している事例を紹介します。
ヤマハ株式会社
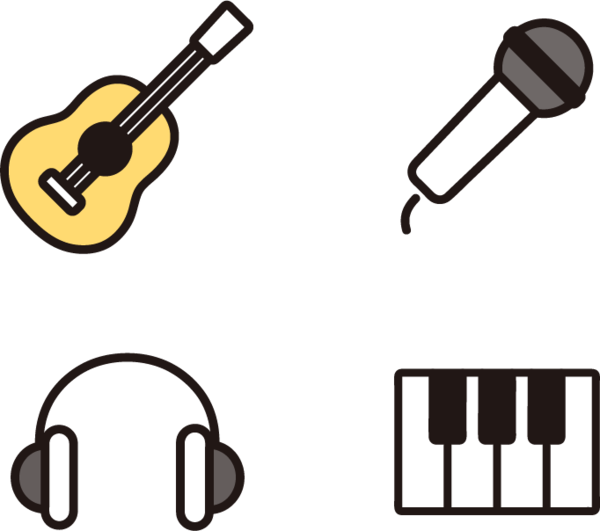
ヤマハは、サステナビリティ活動を「顧客満足の向上」社会的責任(CSR/Sustainability)の項目に含めています。そして、社員一人ひとりが顧客体験の実現を意識し、業務を推進しています。
具体的には、お客様の声を体系的に吸い上げ、商品やサービス開発に取り入れる仕組みを整備。仕組みを作るだけでなく、実際にこの仕組みが機能するように社員向けのトレーニングも実施しています。
さらに、聴覚に不安がある方への音声ガイダンスや、誰でもピアノ演奏が楽しめる自動伴奏機能付きピアノなど、「音楽を楽しむ体験」をより広い層に届ける取り組みを行っています。サステナビリティとCXを掛け合わせた好例といえるでしょう。
サントリー

サントリーはブランドパーパス「水と生きる」、企業理念「人と自然と響きあう」を掲げています。製品そのものが水と自然の恩恵を受けて作られるという認識のもと、製品開発・製造からサステナビリティ活動に至るまで、一貫した姿勢を示しています。
同社の代表的な取り組みは、同社の広告でもおなじみの水資源の保全や愛鳥活動などに代表される自然保護活動です。これらを通じて自然を守り、その恵みを製品作りに活用するという循環を顧客に提示することで、製品そのものの価値以上の「ストーリー」を提供しています。これが結果的にCXを強化する要因となっています。
JTB

JTBは1982年、日本にサステナビリティという概念が広まるはるか前から、サステナビリティ活動を始めています。当初は観光地の清掃活動を中心とした「観光地クリーンアップキャンペーン」でしたが、2012年の創立100周年を機に「JTB地球いきいきプロジェクト」として進化しました。現在では、観光地での環境美化や歴史・文化の学習体験、地域住民との交流など、顧客と社員が共に参加するプログラムを展開しています。
単なる旅行商品の提供にとどまらず、『旅を通じて持続可能な社会に貢献する体験』を創出している点が、CXの差別化につながっています。旅行者にとっても、単なる観光ではなく「意味ある体験」として記憶に残るのです。

サステナビリティは、もはやCSR(企業の社会的責任)活動の延長ではありません。それは顧客体験価値の重要な構成要素となり、ブランドが「選ばれる理由」に直結しています。
顧客は単なる製品やサービス以上のものを求めています。企業の在り方や姿勢に共感できるかどうかが、ブランドロイヤルティを左右し、長期的な支持につながるのです。
未来の市場では、「顧客の心に届く行動」がブランドの命運を決めます。サステナビリティとCXを両輪で強化できる企業こそが、共感と信頼を勝ち取り、持続的な成長を遂げるでしょう。
トレンド・プロでは、マンガを起点として企業の顧客体験価値向上をご支援しています。マンガのようなビジュアルコンテンツを活用することで、ユニークなコンテンツになることはもちろんのこと、より感情に訴える形で伝えることができるようになり、顧客のファン化も期待できます。
もしご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
★資料ダウンロードはこちら:https://ad-manga.com/download_form
★お問い合わせはこちら:https://ad-manga.com/contact



