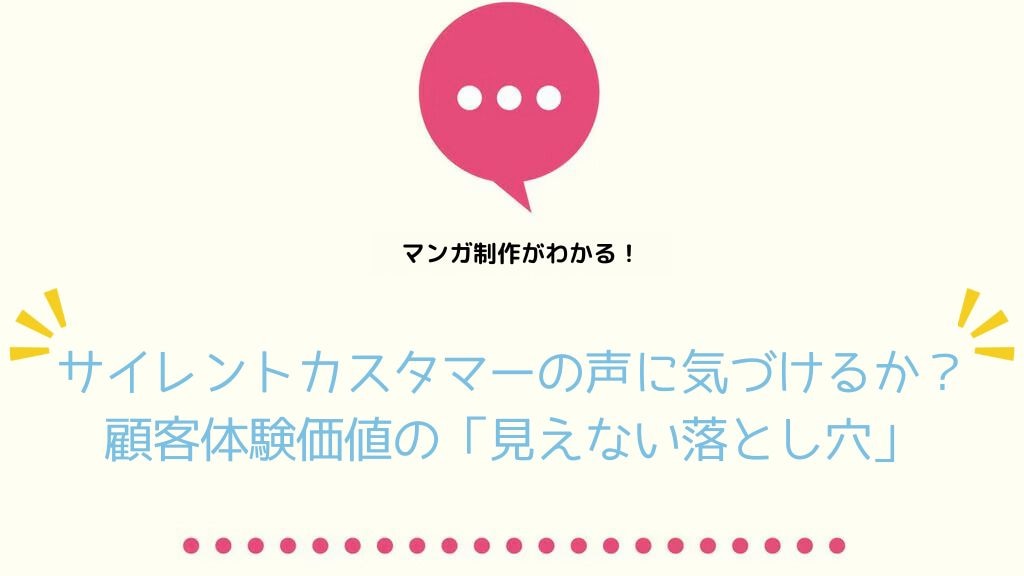
サイレントカスタマーの声に気づけるか?顧客体験価値の「見えない落とし穴」
近年、多くの企業が注力しているテーマのひとつが「顧客体験価値(Customer Experience: CX)」です。商品やサービスそのものの質だけでなく、購入前後の体験全体がブランドの評価を左右する時代。CXを高めることは、もはや競争優位の鍵となっています。
しかし、この流れの中で見落とされがちな存在があります。それが「サイレントカスタマー」です。
彼らは不満を感じてもクレームを言わず、アンケートにも回答せず、ただ静かに離れていきます。企業から見れば「声が聞こえない顧客」であり、気づいたときにはすでに関係が途切れてしまっているケースが多いのです。
本記事では、サイレントカスタマーが生まれる背景と、その兆候を捉えてCX改善に活かすための具体的なアプローチを紹介します。
サイレントカスタマーとは何か
まず、サイレントカスタマーとは何かを把握しておきましょう。サイレントカスタマーとは、簡単にいえば「黙って去っていく顧客」です。
顧客満足度調査で高評価を残す人や、長文の要望を送る人は、企業にとって分かりやすい存在です。しかし、多くの顧客はそこまで声をあげません。「どうせ改善されないだろう」「意見を伝えるのは面倒だ」「最初から期待していない」――そんな心理が働き、不満があったとしても黙って離脱するのみです。
顧客体験価値の観点で考えると、これは大きなリスクです。企業は声の大きい顧客に対応する一方で、声なき顧客の不満を放置し、気づかぬうちにロイヤルティ低下や解約率上昇を招いてしまいます。
なぜ今、サイレントカスタマーに注目すべきか
SNSや口コミサイトが普及したことで、企業にとって顧客の声は把握しやすくなりました。ポジティブな投稿もネガティブな投稿も拡散されやすく、企業はリアルタイムで反応を追うことが可能です。
一方で、その裏側で「声を出さない層」はますます見えにくくなっています。可視化されたクチコミに注目するあまり、沈黙する顧客の離脱を軽視してしまうのです。
その結果として、以下のような状況が生じます。
ロイヤルティが低下する→顧客が離脱する→売上が減少する
企業がサイレントカスタマーを認識せず放置してしまうと、「サイレントな悪循環」に陥ってしまいます。顧客体験価値を真に把握するためには、「声が聞こえない顧客」の存在に目を向けることが欠かせません。
「見えない不満」が生まれやすい、CXの落とし穴
それでは、サイレントカスタマーが生まれる背景には、どのようなCX上の落とし穴があるのでしょうか。以下にその代表的な例を3つ挙げます。
1.一貫性のないコミュニケーション
企業のWebサイトでは丁寧なトーンなのに、チャットやコールセンターに問い合わせをすると事務的。こうした「顧客の期待と現実のギャップ」は無言の不満を引き起こします。顧客はブランド全体をひとつの体験として捉えるため、チャネルごとの温度差は大きな違和感につながります。
2.問い合わせのための導線がわかりにくい
「困ったときにどこに問い合わせればいいかわからない」「回答が返ってくるまでに時間がかかる」。こうした状況は顧客にとって大きなストレスです。結局「もういいや」と離れてしまうケースは珍しくありません。
3.アンケート疲れ・形式的なフィードバック依頼
顧客の声を集める姿勢は重要ですが、形式的なアンケート依頼が続くと逆効果です。「どうせ読まれていない」と思われてしまえば、本音は引き出せず、かえって心が離れていきます。
サイレントカスタマーを捉えるためのアプローチ
声をあげない顧客を完全に可視化することは難しいものです。しかし、その兆候を捉える方法はいくつかあります。
■行動データの活用(定量的アプローチ)
Webやアプリの利用データには、多くの「違和感の兆候」が隠れています。例えば以下のようなものです。
- ページ滞在時間の短縮
- 特定ページでの離脱率の急上昇
- クリックログの偏り
こうした数字の変化を丁寧に追うことで、クレームに至る前の「無言の不満」を早期に察知できます。
■顧客インタビュー・N1分析(定性的アプローチ)
数字に現れない理由を掴むには、少人数でも深掘りインタビューが有効です。個別の体験談を丹念に聞き取ることで、サイレントな声を代弁できる“代表的な不満”が見えてきます。N1分析(ひとりの顧客の体験を徹底的に掘る手法)は、意外な示唆を与えてくれることが多いのです。
■社内における“現場の声”の収集
CX改善は顧客だけでなく、社員の声からも見えてきます。特にフロントラインの社員は、小さな違和感や顧客のちょっとした反応を敏感に察知しています。日常の現場観察を仕組みに組み込むことで、見落としがちな不満をすくい上げることが可能になります。
サイレントカスタマー対応の成功事例
それでは、サイレントカスタマーに対する施策を講じ、実際に成果を上げている企業の例を紹介します。
ニッセン
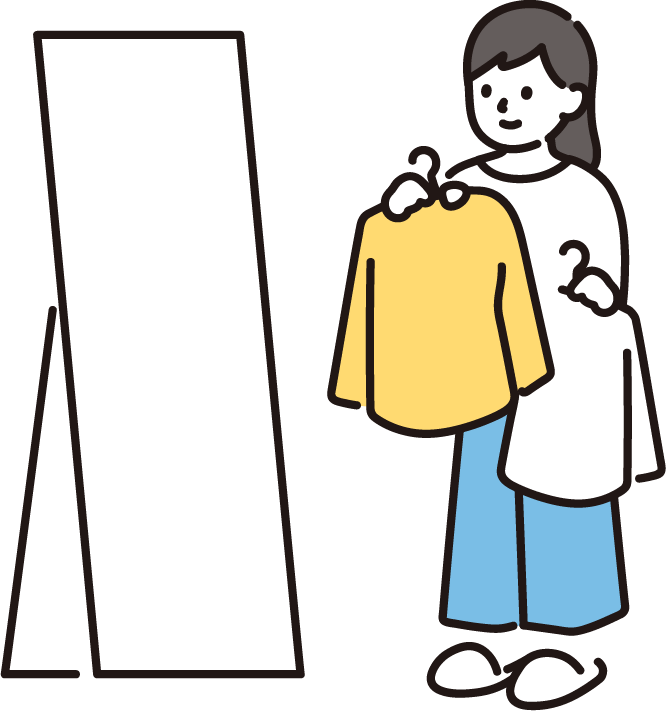
通販大手のニッセンは、問い合わせ対応の効率化を目的に2018年頃からRPAやAIチャットを導入しました。導入後のデータを分析すると、意外な発見があったそうです。
それは、従来の電話やメールに比べ、AIチャット経由では「服のサイズ」や「送料」に関する問い合わせが大幅に増えていたことです。裏を返せば、顧客は“人には聞きづらい”と感じることを、非対人チャネルでは積極的に質問していたということ。これまで表面化しにくかった顧客の不満や疑問が、AIを通じて浮かび上がったといえます。
同社はその知見をもとに、ECサイトの改善や情報設計の見直しに着手。結果的に「声を上げない顧客」のニーズを的確に捉え、顧客体験の向上につなげています。
味の素冷凍食品
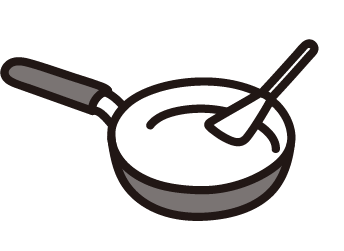
2023年に味の素冷凍食品が立ち上げた「冷凍餃子フライパンチャレンジ」も、サイレントカスタマー対応の好例といえます。そのきっかけは、SNS担当者がX(旧Twitter)で見かけた一件の投稿でした。
「味の素の冷凍餃子を焼いたら、フライパンにくっついてしまった」
今や多くの企業がSNSを運用していますが、顧客投稿を拾い上げ対応する企業は多くありません。しかし、同社はこの声を無視せず「冷凍餃子がくっついたフライパンを送ってください」と呼びかけ、商品改良を行うことを宣言しました。その結果、くっつきを最大で54%改良した商品の発売に成功しています。
今回のケースでは、顧客はXに商品の不満を投稿していました。しかし、担当者がこの投稿に気づかなかったり、気づいたとしても「冷凍餃子は多少フライパンにくっつくもの」と流してしまえば、顧客は不満を抱えたまま沈黙し、やがて離れていくでしょう。声を拾い上げ、行動につなげたことで、単なるクレームが商品革新の起爆剤となったのです。

サイレントカスタマーは、顧客体験価値を高める上で見逃してはならない存在です。「不満のない離脱」を完全にゼロにすることは難しいと考えられます。しかし、その兆候に早く気づき、改善のアクションにつなげることは、CX向上にとって大きな役割を果たします。
顧客体験価値を真に高めるために求められるのは、沈黙している顧客がいると認識し、その沈黙の裏に隠れた意味を読み取る力です。可視化された声だけでなく、聞こえてこない声にも耳を澄ますことで、企業は初めて真のCX向上に近づけるのです。
トレンド・プロでは、マンガを起点として企業の顧客体験価値向上をご支援しています。マンガのようなビジュアルコンテンツを活用することで、ユニークなコンテンツになることはもちろんのこと、より感情に訴える形で伝えることができるようになり、顧客のファン化も期待できます。
もしご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
★資料ダウンロードはこちら:https://ad-manga.com/download_form
★お問い合わせはこちら:https://ad-manga.com/contact



