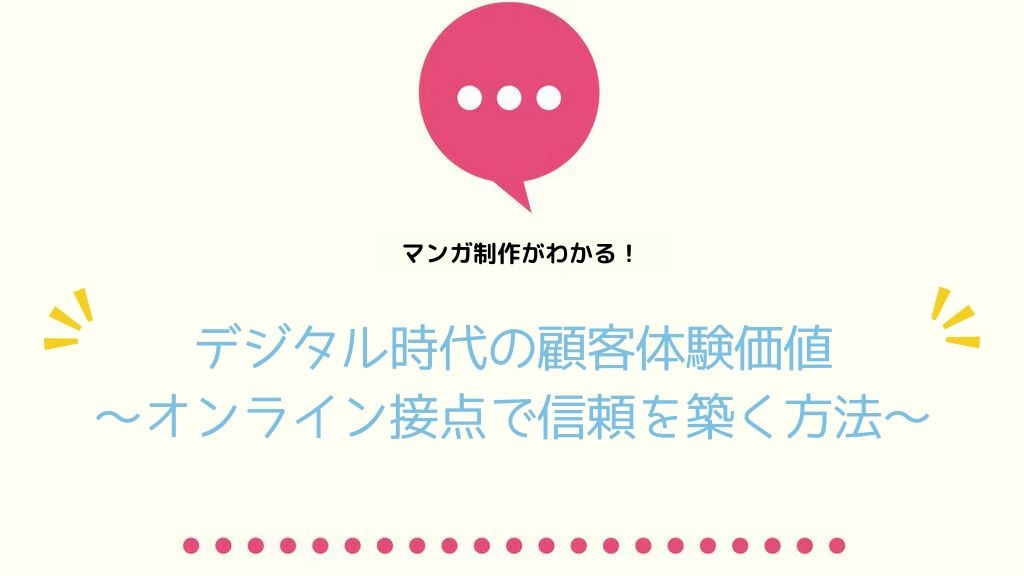
デジタル時代の顧客体験価値:オンライン接点で信頼を築く方法
ビジネスの現場では今、顧客との接点の主流が急速にデジタルへと移行しています。その結果、商品を検索するのも、購入を決めるのも、問い合わせをするのも、多くはスマートフォンやパソコンを通じたオンライン経由になりました。その結果、企業が提供する「顧客体験価値(CX)」の重要性はこれまで以上に高まっています。
顧客体験価値とは、単に「モノを買う」だけでなく、購入前後の一連の体験すべてを含むものです。デジタル接点において、顧客が安心し、信頼を持てるかどうかが、企業の評価を左右する大きな要因となっています。実際、オンライン上で信頼を築ける企業とそうでない企業の差は年々広がっています。
本記事では、Webサイト・SNS・チャットボットといった非対面のデジタル接点を活用しながら、どのように顧客体験価値を高め、持続的な信頼関係を築くのかを解説します。
顧客体験価値とは?〜定義と背景〜
「顧客体験価値(Customer Experience Value)」とは、顧客が企業やブランドとの接点を通じて得る体験の総合的な価値を指します。単に商品やサービスの性能や価格だけでなく、購入前の検索体験、問い合わせ時の対応、購入後のフォローに至るまで、そのすべてが体験価値を形成します。
現代においては、商品自体の差別化が難しくなっています。似たような品質や価格帯の製品が市場に溢れる中で、顧客が選択基準とするのは「どんな体験を得られるか」です。たとえば、同じ商品を購入するなら、わかりやすい説明やスムーズな購入フローを提供する企業のほうが選ばれる傾向にあります。
デジタル環境では、体験の始まりと終わりが曖昧です。SNSでブランドを知り、Webサイトで比較検討し、購入はECサイトで行い、アフターフォローはチャットで――こうした流れが一般的になっています。このように多様な接点のすべてが「顧客体験価値」を構成するため、企業は一貫した体験設計を求められているのです。
なぜ今「デジタル」でのCXが重要なのか
新型コロナウイルスの影響をきっかけに、デジタル接点は急速に主流化しました。店舗に足を運ばなくても商品を購入でき、SNSで企業の評判を確認し、問い合わせはチャットやメールで完結する。この変化は一時的なものではなく、生活者の購買行動として定着しています。
特に、顧客行動は「非対面化」「短時間化」「多チャネル化」が進みました。時間をかけて店舗で説明を受けるよりも、スマホで数分調べて即決するケースが増えています。その際に重要なのは「いかにストレスなく、わかりやすく、安心して行動できるか」という体験です。
企業と顧客との接点は、もはや店舗ではなく「スマホの中」にあります。だからこそ、デジタル上でのCXが競争力を左右します。実際、顧客は企業の対応スピードや一貫性を敏感に評価しており、「迅速に答えを得られる」「どのチャネルでも同じ品質の対応がある」企業ほど信頼を得やすいのです。
非対面接点におけるCX設計の要点
ここからは、非対面接点ごとにCXを設計する際にポイントとなる点を紹介します。
1) Webサイト編
Webサイトは企業の「顔」であり、ファーストビューでの印象が信頼を大きく左右します。デザインが古い・スマホで見づらい・情報が散在している――こうした体験は即座に離脱につながります。
特に重要なのは以下の3点です。
- スマホ対応:モバイルファースト設計は必須。レスポンシブ対応や読み込み速度を最適化する。
- UI/UX設計:直感的に操作できるナビゲーション。ユーザーが迷わない導線づくり。
- 情報設計:「伝えたいこと」より「読み手が知りたいこと」を優先する。FAQや事例、比較表など、意思決定を助けるコンテンツを用意する。
2) SNS編
SNSは顧客と”会話”をする場です。単なる宣伝媒体ではなく、共感や透明性を示すコミュニケーションの場として設計する必要があります。
- 共感性:企業の姿勢や価値観を発信し、顧客の関心や感情に寄り添う。
- タイムリーさ:迅速な情報更新やレスポンスが信頼につながる。
- エンゲージメント活用:いいねやコメントといった顧客の反応は「顧客体験の一部」として捉え、商品開発やサービス改善に反映する。
3)チャットボット編
チャットボットは24時間対応が可能で、顧客に「便利さ」「安心感」を与える大きな役割を果たします。ただし「無機質な自動応答」にならない工夫が求められます。
- FAQ設計:よくある質問に的確に答えられるように整備する。
- 有人対応への切替:解決できない場合はスムーズに担当者へつなげる。
- 温かみの演出:文体を丁寧にしたり、絵文字やビジュアルを使うことで、冷たさを和らげられる。
▶︎チャットボットにも!キャラクター制作・活用についてはこちら
非対面接点においては「顧客に寄り添っている感覚」をどう伝えるかがCX設計の核心といえます。
CX向上の成功事例
ここからは、非対面接点を導入することでCXを向上させることに成功している企業の例を紹介します。
スターバックスのアプリ体験

スターバックスは、アプリを通じてモバイルオーダーや事前決済を可能にし、店舗での待ち時間を短縮しました。さらに、買い物をするとたまるStar(ポイント)をオリジナルグッズと交換できたり、アプリ経由で新製品の先行販売を経験できたり、訪れた店舗を写真と共に記録できたりと、アプリユーザーならではの特別な体験を提供しています。
これらの結果としてスターバックスはアプリユーザーに「利便性」と「特別感」の両方を提供することに成功しました。
ユニクロのオンライン接客

ユニクロは公式アプリやECサイトにおいて、チャットボットを活用した商品検索やサイズ相談を導入。さらに有人チャットでの対応も整備し、顧客が安心して購入できる環境を実現しました。これにより「店舗に行かなくても納得して買える」という顧客体験価値を提供しています。
Zapposのカスタマーサポート

米国のオンラインシューズ販売大手企業であるZapposは、顧客サポートを単なる問い合わせ対応ではなく「ブランド体験の場」と位置付けています。
チャットはもちろんのこと、コールセンターも24時間対応で迅速かつ親身。そこから、個別に対応すべきと判断した顧客にはオンラインを超えたサービス提供するなど、きめ細やかでユニークなサービスで知られています。多くのBtoC企業にあるであろう顧客対応マニュアルやトークスクリプトは常備しておらず、サポートチームは日々目の前の顧客にどう対応したら喜ばれるかを考え、実行しています。
このように、Zapposは「顧客第一主義」を体現することで、熱狂的なファンを獲得することに成功しています。その結果、Zapposの新規顧客獲得の43%が口コミ、顧客のリピート率が75%という驚異的な数字を誇っています。
これらの事例からわかるのは、デジタル接点においても「便利さ」と「人間らしさ」を両立させることが、顧客体験価値を高めるポイントだということです。

デジタル化が進んでも、顧客体験価値の本質は「人と人との信頼関係」にあります。オンライン上のWebサイトやSNS、チャットボットは、あくまでその信頼を築くための手段にすぎません。
企業に求められるのは、顧客の声に耳を傾け、常に改善を続ける柔軟性です。小さな接点の積み重ねがブランドへの信頼につながり、長期的な関係を築きます。
デジタル時代におけるCXは一度作って終わりではなく、顧客の行動や期待に応じて常に進化していくものです。日々の接点の一つひとつが「信頼づくり」であることを意識し、企業はCX向上を継続的に取り組む必要があります。
トレンド・プロでは、マンガを起点として企業の顧客体験価値向上をご支援しています。マンガのようなビジュアルコンテンツを活用することで、ユニークなコンテンツになることはもちろんのこと、より感情に訴える形で伝えることができるようになり、顧客のファン化も期待できます。
もしご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
★資料ダウンロードはこちら:https://ad-manga.com/download_form
★お問い合わせはこちら:https://ad-manga.com/contact



