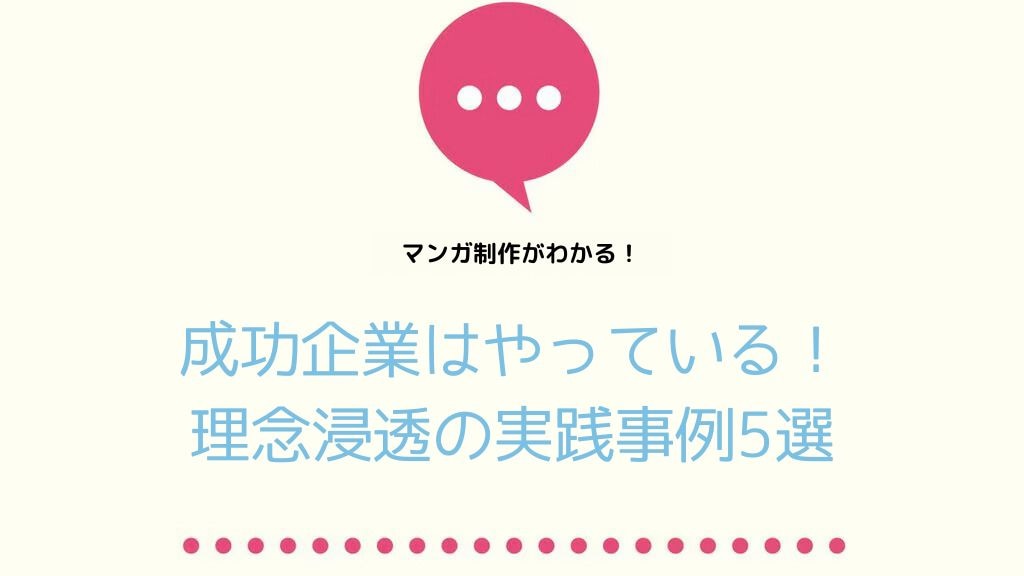
成功企業はやっている!理念浸透の実践事例5選
企業理念は、単なるスローガンではありません。企業が何のために存在するのか、どんなことを目指すのか、そしてどのような価値観を大切にするのかなどを含むものであり、組織の「軸」となるものです。
しかし、理念を策定するだけで満足していないでしょうか?
実際の現場では、「理念があることは知っているが、普段の業務とは関係がない」「理念が日々の行動にどうつながるのか分からない」といった声が聞かれることも少なくありません。理念は、社員一人ひとりの行動や意思決定の基準として機能してこそ、初めて価値を持ちます。
そこで今回は、「理念浸透」に成功している企業の具体的な事例を5つ紹介し、どのような工夫や仕組みで社員に理念を浸透させているのかを解説し、自社で理念を根づかせるためのヒントもまとめています。本記事を企業理念の浸透のためにぜひ参考にしてください。
企業理念浸透の重要性とは?

まず、そもそも企業理念の浸透とは何を指すのかを整理しましょう。
企業理念浸透とは、企業のミッション(使命)、ビジョン(目指す姿)、バリュー(価値観)を、社員一人ひとりが理解し、日々の判断や行動に反映させている状態を指します。理念が浸透すると、組織には以下のようなポジティブな効果が生まれます。
〈理念浸透すると生まれるポジティブな効果〉
・企業文化の醸成:共通の価値観が根づき、社員同士の連携や信頼感が高まる。
・エンゲージメント向上:自社の方向性に納得し、使命感を持って働く社員が増える。
・一貫した意思決定:個々の判断が理念に基づくため、組織全体で「ぶれない行動」が可能となる。
一方で、理念が表層的で、社員が心から納得することなく放置されていると、以下のような課題が生じます。
〈理念浸透していないと…〉
・組織の方向性が社員に伝わらない
・「なぜこの仕事をするのか」が不明確になり、モチベーションが低下する
・ 社員の価値観がバラバラになり、内向きな対立や混乱が生まれる
つまり、理念は掲げて満足するものではなく、浸透させて初めて意味があるものなのです。
理念浸透の成功事例5選
ここでは、理念浸透において高い成果を上げている5つの企業の取り組みをご紹介します。
■サイボウズ株式会社:「理念に共感できなければ、入社しないでください」
サイボウズは「チームワークあふれる社会をつくる」という企業理念を掲げ、組織文化の中核に据えています。同社の最大の特徴は、「理念に共感できる人材だけを採用する」という方針を徹底していることです。
採用段階でのフィルタリングだけでなく、入社後も定期的に理念について話し合う時間を設け、全社員が理念を自分ごととして捉えられる仕組みを構築しています。
▷ポイント: 「理念に共感できる人材」を最初から採用することで、文化の一貫性を守る
■清水建設株式会社:ストーリーマンガで理念の“共感”と“体感”を促進
清水建設は「働きがいと魅力あふれる職場づくり」をスローガンに掲げ、従業員間のコミュニケーション促進や働きがいの向上に向けた取り組みを進めています。その一環として、マンガを活用した施策を導入。トレンド・プロでは第1弾から第3弾までのマンガ制作を担当しました。
マンガのストーリーを通して、従業員に取り組みを「自分ごと」として捉えてもらい、具体的な行動につなげることを目指しました。そのため、ストーリーには現場で実際に起きる出来事を反映させ、登場人物やシチュエーションにリアリティを持たせることに注力。
マンガを全従業員に配布したところ、その後に実施したアンケートでは9割の従業員が「読んだ」と回答しました。
感想としては、「短時間で内容を理解できる」「実務に近く、すぐに役立てられる」といった肯定的な意見が多く寄せられました。
▷ポイント:理念をストーリーで“体感”させ、理解から行動へとつなげる仕組みづくり
■株式会社ユーグレナ:複数のツール活用で理念を「見える化」
ユーグレナは、2020年に創業15周年を迎えたことに合わせ、企業理念を「Sustainability First」へと刷新し、社内ワークショップや社員間での議論を通じ、浸透を図りました。
同社の理念浸透施策の特徴は、社員が理念に基づく行動を取りやすいよう、さまざまなツールを通じ支援していること。例えば、社内からペットボトル容器を撤去してウォータースタンドを導入したり、「ナカマブック」と呼ばれる冊子を配布したり、オンボーディング研修やマインドセット研修を実施し、理念浸透を強化したりしています。
▷ポイント:理念を「見える化」し、日常業務に落とし込むことで行動変容を促す
■パナソニックホールディングス:「綱領・信条」の再定義で理念をアップデート
パナソニックホールディングスには長年、創業者・松下幸之助によって確立された経営理念、そしてその根幹となる「綱領・信条・七精神」があります。しかし、これらは昭和初期につくられたものであり、現在の価値観からすると距離感を感じることは否定できません。
そこで、2021年にこれらを現代に即した文脈で再定義し、大改訂を行いました。これにより、社員が現在の社会課題や価値観と結びつけて理解できるよう配慮されています。
また、社内イベントやオンライン研修を通じて、全社員が理念について語り合う機会を数多く設けているのも特徴です。
▷ポイント:古くなった企業理念を現代文脈で再構築し、社員との距離を縮める
■スターバックスコーヒー ジャパン:理念を行動に変える多重構造の仕組み
スターバックスでは、「この一杯から広がる、心かよわせる瞬間、それぞれのコミュニティとともに―人と人とのつながりが生みだす無限の可能性を信じ、育みます」というミッションが全スタッフに共有されています。
それだけではなく、新人スタッフに対する研修の実施、行動指針に沿った行動をしたスタッフに渡す「グリーンエプロンカード」の常設、4ヶ月ごとの1on1の実施、理念を体現できる行動「スタースキル」を明文化し、スタッフのコミュニケーションに取り入れるなどの活動を行っています。
このように、ミッション・バリューの明文化 → 長時間研修 → 日々のツール・面談 → 評価制度という多層構造アプローチによって、理念を「覚えるもの」ではなく「日々の行動として当たり前のこと」にしています。
▷ポイント: 多重構造の仕組みを構築し、自然に理念を実践できる循環をつくる
まとめ──理念浸透を加速させる実践ポイント
それでは、自社で理念浸透を実行する際にはどんな点に気をつければよいのでしょうか。
ここまでに挙げた5つの企業の成功事例から見えてくる理念浸透のカギは「一貫性」と「日常化」です。
以下の3つのポイントを押さえることで、自社でも理念の浸透を加速させることができます。
1.トップダウンとボトムアップの融合
経営層から理念を強く発信するだけでなく、現場からの共感と自発的な実践を引き出す仕組みが重要です。トップだけが語るのではなく、社員自身が「自分の言葉」で理念を語れる状態が理想です。
2.日常的なコミュニケーションへの組み込み
企業理念が浸透している企業では、理念は掲示物ではなく、従業員の日常的な会話の中に存在しています。朝礼、ミーティング、社内報、1on1など、日々のさまざまなコミュニケーションの中で理念を取り上げる工夫が求められます。
3.人事評価制度への反映
人事評価制度において、理念に基づく行動を評価項目に組み込むことで、社員が「理念に沿った行動」を日常的に意識するようになります。これは、行動変容を促す強力なドライバーとなります。

ここまでに何度も繰り返していますが、理念は「飾るもの」ではなく、「使うもの」です。理念が社員の行動に自然と現れるようになったとき、組織は本当の意味で「軸」を持つことができます。
本記事で紹介した理念浸透の事例を参考に、自社に合った取り組みを見つけ、実践してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせはこちら:https://ad-manga.com/contact



